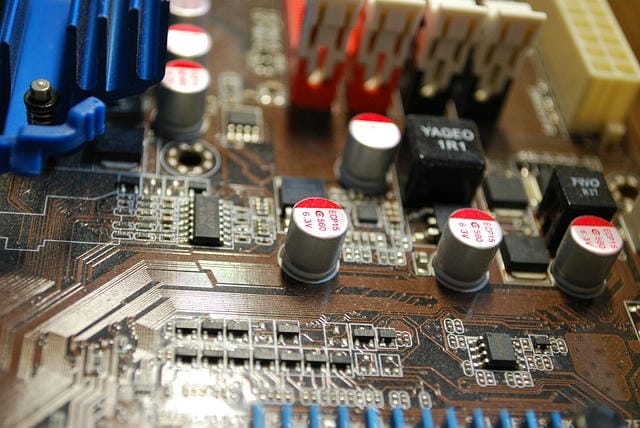従来の情報システムにおいては、企業や組織のネットワークはオフィス内部で完結し、その境界に様々な防御策を施して保護する方法が主流であった。たとえば、ファイアウォールや侵入検知システムなどが設置され、内部と外部との通信を制限・監査することでセキュリティを維持していた。しかし業務アプリケーションのクラウド化やテレワークの普及、社外からの多様なアクセスニーズの拡大により、もはや境界だけを守る発想では業務遂行に必要な柔軟性や十分な安全性が確保困難となった。このような背景により、複数の領域や地点、デバイスから企業データへの利用が常態化すると、どこからでも同水準の厳格なアクセス制御や通信暗号化、ネットワーク監視が不可欠となる。その要望に応える概念として登場したのがSecure Access Service Edgeと呼ばれる新しい枠組みである。
これは、ネットワーク機能とセキュリティ機能を統合し、一元的かつ柔軟に提供する点が大きな特徴となっている。具体的には、仮想的な「縁」すなわちエッジの役割を利用して、組織の拠点・モバイル端末・各種クラウドサービスのどこからでも均一で細分化されたセキュリティ機能にアクセスできるよう設計されている。ここで言うセキュリティ機能には、悪意ある侵入検知、マルウェアやウィルスの検知・防御、利用者ごとのアクセス制御、データ暗号化、通信トンネリング、脅威インテリジェンスの参照と反映などが含まれる。こうした多様な機能を一体化してネットワーク利用時に中継ポイントとなるクラウド基盤上で提供することが大きな利点となる。この枠組みの効果としては、従業員や外部委託先が自宅や外出先など組織外部からクラウドや社内システムに安全に接続できる環境が構築可能である。
また、従来必要とされた複数拠点ごとのセキュリティ装置・ネットワーク管理設備を大幅に削減できる点も負担軽減に寄与する。異なる場所や端末からのアクセスも一律の基準で判定され、適切な認証やログ監査によって情報漏洩や未承認利用を未然に察知できる仕組みとなっている。クラウドサービス利用では、各業務アプリケーションが生産性向上の決定要素であり、利用するサービスは今後も複雑化が進む。そのため、アプリケーションごとの通信監視や動的な制御・可視化、ユーザーやデバイス単位での高度な識別技術の応用も重要である。そこにSecure Access Service Edgeの技術が応用されることで、ユーザーごと・アプリケーションごとといった粒度の細かい利用制御や、基準違反時の即時遮断といったリアルタイムな対応も容易となった。
さらに、従来型の境界防御モデルが苦手とする未知の脅威や標的型攻撃にも、脅威検知情報のクラウド統合や可視化ダッシュボード等により早期に察知・封じ込め可能である。これらを踏まえれば、組織固有のネットワーク構造や勤務実態の変化に柔軟に追従しつつ、全体のセキュリティ水準を維持・強化できるのがSecure Access Service Edgeの最大の魅力である。しかし、導入・運用にあたり留意すべき点もある。その一つがインターネット回線品質やクラウド側のパフォーマンス維持であり、全ての通信や認証処理がクラウド経由となることへの考慮が必須である。また、セキュリティ機能の一部をアウトソースする構造になるため、自社ポリシーや法的要件との整合性検証やID管理との連携強化も重要となる。
これらの課題をクリアすれば、分散した利用環境下でも一貫した情報保護基盤を築くことができ、クラウド型業務推進を阻害せずに安全性を確保できる。最後に、これまで現場での体感としても、多拠点やリモートワーク主体の組織においては、従来の境界防御方式と比べはるかに速効性かつ柔軟性のあるセキュリティ対応が実現しており、新たな脅威にも素早い対処が可能となっている。クラウドへの安全な接続、多様な従業員や協力会社との共同作業、基準を満たす運用監査を継続できることは、有形無形の財産を守る現場にとって欠かせない要素であり、Secure Access Service Edgeの価値が今後ますます発揮されていくと考えられる。従来の情報システムでは、オフィス内部に設置されたネットワークの「境界」を防御する方法が主流でしたが、業務アプリケーションのクラウド化やテレワークの普及により、この考え方だけでは安全性と柔軟性を両立できなくなっています。現在では、拠点やデバイスが多様化し、社外からのアクセスも日常化しているため、一元的かつ均一なアクセス制御や暗号化、監視の必要性が高まりました。
こうした背景のもと登場したSecure Access Service Edge(SASE)は、ネットワークとセキュリティ機能をクラウド上で統合的に提供し、どこからでも均一なセキュリティ管理を可能にします。SASEでは、悪意ある侵入やマルウェア検知、細かなアクセス制御や暗号化、通信トンネリングなど多様な機能がクラウド上の中継ポイントを通じて提供されます。これにより、社外からの安全なアクセス環境を実現し、従来必要だった拠点ごとのセキュリティ投資を抑制できる点も大きな利点です。また、ユーザーやアプリケーション単位での詳細な制御や、リアルタイムな対応も可能となっています。さらに、未知の脅威や標的型攻撃対策にもクラウドベースの情報共有や可視化機能で素早く対応できるなど、柔軟性と堅牢性が両立できます。
ただし、全通信のクラウド経由化やアウトソースによるポリシー・法令順守の確認、ID管理連携など導入時の留意事項もあります。これらを適切に管理すれば、分散した働き方や多様な業務環境にも適合した強固な情報保護体制が構築でき、今後のビジネスに不可欠な基盤となると言えます。